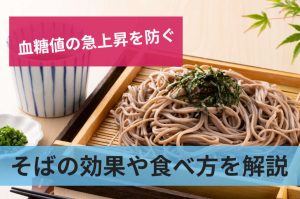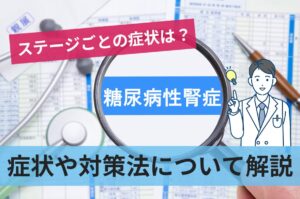牛乳は豊富な栄養を含む飲料であり、骨や歯を作るために必要なカルシウムを確保できます。
糖尿病に対しても有効な成分があると研究結果が出ているため、血糖値の高さが気になる人にも推奨される飲料です。
しかし、牛乳の種類や飲む人の体質によっては、飲み過ぎると悪影響が出る可能性もあります。
この記事では、牛乳の血糖値に対する影響や主な健康効果、取り入れる際の商品の選び方などをまとめました。
- 牛乳の主な栄養素と健康効果
- ヨーグルトドリンクや豆乳との違い
- 1日で飲む適量や健康効果を得られる時間帯
- 牛乳でお腹の調子が悪くなる人の原因と対策
糖尿病や血糖値上昇の予防として牛乳を積極的に取り入れたい人は、参考にしてください。
牛乳はカルシウムとたんぱく質を多く含む飲料である

牛乳は牛の乳汁を原料とし、栄養価の高い飲料として農林水産省では毎日の摂取を推奨しています。
牛乳100mlあたりに含まれる主な栄養素は、以下のとおりです。
| 100mlあたり | 普通牛乳 |
|---|---|
| カロリー | 61kcal |
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.8g |
| 食物繊維 | – |
| 炭水化物 | 4.8g |
| ナトリウム | 41mg |
| カリウム | 150mg |
| カルシウム | 110mg |
| マグネシウム | 10mg |
| リン | 93mg |
| 鉄 | – |
栄養素の中でもカルシウムやたんぱく質が多く含まれており、2つの成分は糖尿病や血糖値に対して良い効果を発揮します。
カルシウム以外のミネラル成分も多く、身体づくりやエネルギー源としても役立ちます。
牛乳は低GIや豊富なたんぱく質が糖尿病や血糖値に良い影響を与える
牛乳は以下の点から、糖尿病や血糖値に良い影響を与える研究結果が出ています。
- 低GIの継続的な摂取で糖尿病発症リスクの減少
- たんぱく質は消化に時間がかかり、食前に飲むと糖質の消化を遅らせて血糖値の上昇を緩やかにできる
GI値は食後血糖値の上昇量を示す数値であり、牛乳のGI値は27です。
GI値が55以下の食品は低GI食品に分類され、血糖値の上昇が緩やかで負担が少ないとされています。
牛乳に含まれる豊富なたんぱく質も血糖値の上昇を抑制する効果があるため、低GI食品と併せて糖尿病予防が可能です。

牛乳のような低GI食品に加えて、ポリフェノールを含む食品も血糖値のコントロールに役立つといわれています。
最近では、ポリフェノールの血糖抑制作用に関する研究も進められています。
糖尿病予防におけるポリフェノールの最新研究はこちら
糖尿病患者でリスクが高い骨折についても牛乳が効果的である
糖尿病を発症すると骨粗しょう症や骨の質が悪化する傾向があり、発症前よりも転倒や骨折リスクが高まります。
糖尿病患者が骨の強度を保つためには、血糖コントロールを行いながら、骨の質を高める治療が必要です。
研究結果においても牛乳などの乳製品を毎日摂取すると、骨量の減少を抑えつつ、脚や腕の筋肉を維持できるという結果が出ています。
そのため、糖尿病予防だけでなく、糖尿病患者の健康維持でも有用な飲料です。
牛乳はヨーグルトや豆乳と比べて乳糖やカルシウムの量が多い


健康効果を得られる飲料として、同じ乳製品のヨーグルトドリンクや豆乳が比較対象にあげられる場合があります。
牛乳とヨーグルトドリンクや豆乳を栄養素で比較すると、以下のとおりです。
| 100mlあたり | 普通牛乳 | ヨーグルトドリンク | 豆乳 |
|---|---|---|---|
| カロリー | 61kcal | 64kcal | 43kcal |
| たんぱく質 | 3.3g | 2.9g | 3.6g |
| 脂質 | 3.8g | 0.5g | 2.8g |
| 食物繊維 | – | – | 0.9g |
| 炭水化物 | 4.8g | 12.2g | 2.3g |
| ナトリウム | 41mg | 50mg | 2mg |
| カリウム | 150mg | 130mg | 190mg |
| カルシウム | 110mg | 110mg | 15mg |
| マグネシウム | 10mg | 11mg | 25mg |
| リン | 93mg | 80mg | 49mg |
| 鉄 | 0mg | 0.1mg | 1.2mg |
牛乳とヨーグルトドリンクは原料が同じで100mlあたりのカルシウムの量も変わりませんが、ほかの栄養素では数値の差が出ています。
乳糖は炭水化物の1種であり、健康面では以下の効果があります。
- 乳糖分解酵素により分解、吸収されてエネルギー源になる
- 腸内細菌の餌になり、有害な細菌の繁殖を抑える
- カルシウムやマグネシウム、鉄の吸収を高める
乳糖はヨーグルトにも含まれていますが、乳酸菌で一部が分解されるため、牛乳よりも含有量が減ります。
牛乳と豆乳の主な違いは、原料と主要な成分です。
牛乳は動物性の乳汁が原料であり、カルシウムとたんぱく質が多く含まれています。
一方、豆乳は植物性の食品であり、牛乳よりもカロリーや脂質は低いですが、カルシウムは含まれていません。
カルシウムとたんぱく質の量を確保しつつ、乳糖の効果を重視する場合は、牛乳が適しているでしょう。
牛乳は1日コップ1~2杯を目安にして脂質過多にならないように飲む
牛乳の健康効果を得るためには、コップ1杯を200mlとして、1日あたりコップ1〜2杯が適量とされています。
糖尿病予防や血糖値の上昇抑制を目的に牛乳を飲む場合でも、適量は変わりません。
肥満は血糖値を下げるホルモンのインスリンに悪影響が出るため、脂質の摂取量はなるべく抑えたほうが良いでしょう。
牛乳の種類を選ぶ際は、以下の基準を参考にしてください。
- 食生活が乱れていない場合:低脂肪や濃厚などの表記がない普通牛乳
- ほかの食事や飲み物で脂質を摂取する傾向がある場合:低脂肪や無脂肪
- 健康面では飲むのが推奨されない商品:濃厚や特濃
濃厚や特濃といった用語が使われている牛乳は加工乳であり、脂質分が増えています。
普通牛乳と同じ感覚で飲むと脂質過多になる可能性があるため、健康目的では避けたほうが良い商品です。
普通牛乳と低脂肪、無脂肪牛乳は、普段の食事で摂取する脂質量から自分に合う商品を判断します。
血糖値の上昇を抑える点では牛乳を食前に飲むと効果的である
牛乳を飲むタイミングは、血糖値の上昇を抑える点で考えると、食前に飲むのが推奨されます。
1日1杯飲む場合、時間帯はいつでも構いませんが、食事量が多い時間帯に合わせられるとより効果を発揮します。
一般的に昼食と夕食は食事量が増える傾向があるため、食事の準備時間や食前に牛乳を飲んでおくと良いでしょう。
血糖値の上昇抑制以外の効果で考えると、朝に飲むとエネルギー源になり、夜に飲むと骨や筋肉の形成につながります。
飲む時間帯以上に、毎日継続して適量を飲み続けるのが重要であるため、自分が無理なく飲める時間帯で継続してください。
牛乳でお腹の調子が悪くなる場合は小分けにして飲むか料理に加えると良い


牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる人は、体内の乳糖分解酵素が少ない、もしくは働きが弱いのが原因です。
乳糖分解酵素の働きが弱い場合、摂取した牛乳の乳糖が腸を刺激して便意を促して、腹痛を引き起こします。
牛乳でお腹の調子を悪くしないための対策は、以下のとおりです。
- レンジなどで温めて飲む
- 1日200mlを朝昼晩と小分けにして飲む
- コーヒーや紅茶に混ぜる
- 料理に加える
加熱や少量で飲むと腸への刺激が弱まり、腹痛が起こる可能性を減らせます。
ただし、上記の工夫をしても体質的に牛乳と相性が悪い人もいます。
体質的に合わない人は、血糖値の上昇抑制のために無理をして牛乳を飲み続けるよりは、同じ乳製品のヨーグルトなどに切り替えてください。
糖尿病や高血糖で治療をしている人は牛乳の摂取を病院で相談する
牛乳は糖尿病や血糖値以外にも健康効果を得られるため、記事を読む前から取り入れていたという人も多いでしょう。
しかし、高血糖と診断された人や糖尿病治療を受けている人は、自己判断で牛乳の摂取量を増やすのは推奨できません。
牛乳に限らず、食事や飲料で糖尿病や血糖値の改善を行う場合は、病院で医師や栄養士に相談してから実践してください。
食事で摂取するほかの栄養素や、薬による血糖値調整から判断された適切な摂取量を把握できます。



糖尿病予防のためには、食事全体で血糖値を上げにくい栄養素を意識することが大切です。
近年では、ポリフェノールが糖の吸収を抑えたり、インスリンの働きを高めるといった研究も報告されています。
ポリフェノールの働きと糖尿病予防の関係について詳しく見る
牛乳は毎日飲み続けると糖尿病予防や血糖値の上昇抑制につながる
牛乳は血糖値の上昇が緩やかな低GI食品に分類されており、継続的な摂取は糖尿病の発症リスクを抑える効果もあります。
豊富に含まれるたんぱく質も血糖値の上昇抑制に効果的であり、カルシウムなどの複数の栄養からも健康効果を得られます。
ただし、体質によっては牛乳でお腹の調子が悪くなる場合があるため、合わない場合はほかの飲料への切り替えも検討してください。
1日あたりの摂取量はコップ1〜2杯が適量であり、商品としては普通牛乳や低脂肪、無脂肪牛乳が候補です。
食前に飲むのが推奨されますが、飲む時間を確保できない場合は、自分が無理なく飲める時間で毎日の摂取を継続しましょう。