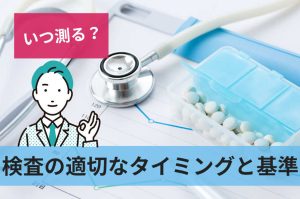みかんは糖分を多く含む果物であるため、血糖値を上昇させてしまうと認識している人が多いのではないでしょうか。
糖尿病になってしまい、大好きなみかんを我慢しなければならないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、実はみかんは血糖値にとって敵ではなく、工夫次第で健康的な食生活をサポートする味方となりえる食材です。
今回は、みかんが血糖値に与える影響について解説します。
血糖値管理に適したみかんの食べ方や、専門家との連携の重要性などについても紹介します。
- みかんは糖質を含むが血糖値上昇を抑える効果もある
- みかんは活用次第で糖尿病予防として効果がある
- 食べる量やタイミング次第で血糖値管理に効果を発揮する
- みかんは血糖値管理の面で敵という認識は誤解
- 血糖値管理には専門家との連携が重要
- みかんは血糖値管理以外にも多くの効用をもつ
今回の記事を参考にして、みかんを上手に取り入れて食生活を楽しみながら血糖値管理に努めましょう。
みかんが血糖値に与える影響について正しい理解を深めよう

糖質を含む食材は、血糖値に何らかの影響を与えるのが一般的です。
果物は甘味が強いため糖質を多く含み血糖値を上昇する作用があると考える人も多いでしょう。
みかんも果物の一種であり、糖質を含む食材であるため、血糖値上昇の作用をもっているのは否定できません。
しかし、糖質を含んでいるというだけでみかんを避けるのは誤りです。
みかんが血糖値に与える影響を正しく理解するため、以下の3つの視点で解説します。
- みかんには糖質が含まれているが比較的少ない
- みかんのGI値は低く急激な血糖値の上昇につながらない
- みかんは血糖値上昇を抑える効果のある食物繊維を豊富に含む
以下の記事を参考にして、みかんと血糖値の関係を正確に理解してみてください。
みかんには糖質が含まれているが比較的少ない
みかんには、一般的な果物と同様、糖質が含まれています。
みかんを食べると、糖質を多く摂取してしまうと考える人もいるのではないでしょうか。
以下に、100g当たりの代表的な果物の糖質量をまとめています。
| バナナ | 19.4g |
|---|---|
| ぶどう | 17.0g |
| りんご | 12.9g |
| みかん | 9.2g |
主要な果物の中では、糖質は多くありません。
みかんは甘味が強く糖質が多い印象をもたれるケースが多い果物ですが、実はそれほど糖質を含んでいません。
みかんのGI値は低く急激な血糖値の上昇につながらない
みかんのGI値は低いため、血糖値を急激に上昇させる心配は少ないです。
ブドウ糖を100の基準として、食品ごとの血糖値の上昇速度を数値化しています。
一般的に、GI値が55を下回っている食品は、低GI食品と分類されています。
みかんのGI値は33であり、果物の中でも低GI食品の代表例です。
バナナやパイナップルがGI値で50を超えているのを考えると、みかんのGI値が低いと分かります。
みかんは、GI値の面からみても血糖値上昇の影響が少ない食品といえるでしょう。
みかんは血糖値上昇を抑える効果のある食物繊維を豊富に含む
みかんには、食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維はゆっくりと消化されて糖質の吸収を遅らせる作用があり、血糖値上昇を抑える栄養素の1つと考えられています。
特に、みかんの果肉よりも薄皮や白い筋の部分に食物繊維が豊富に含まれているため、可能な限り薄皮の部分を残したまま食べると効果的です。
食物繊維は、水溶性と不溶性の2種類がありますが、みかんは両方を豊富に含有しています。
血糖値の管理においては、特に水溶性食物繊維が有効に働きます。
腸内で水分を吸収して膨張し、糖質の吸収を遅らせる効果があるためです。
豊富に含有されている食物繊維が血糖値管理の効果を発揮するため、みかんは血糖値上昇を抑える作用をもつ食材といえるでしょう。
実はみかんは血糖値上昇を抑え糖尿病予防に効果のある食材

糖尿病になった人は、果物など糖質を含む食材を制限する必要があります。
糖尿病予防を目的に、血糖値上昇につながる食材を減らしている人も多いのではないでしょうか。
血糖値を気にする人にとって、みかんは糖質を含んでいる果物であるため、避けたほうがよいと考えるケースも多いかもしれません。
しかし、実はみかんは血糖値上昇を抑え、糖尿病予防に効果があると食材と考えられます。
みかんがもつ血糖値上昇を抑える効能について、以下の3点から解説をします。
- みかんに含まれる栄養素のうち糖尿病予防効果のあるものは多い
- みかんの果実のみでなく薄皮などにも豊富な栄養素が含まれる
- 他の果物と比較してもみかんは血糖値管理に効果がある
以下の内容を参考に、みかんの血糖値に与える効果について理解を深めてください。
みかんに含まれる栄養素のうち糖尿病予防効果のあるものは多い
みかんには、糖尿病予防効果をもつ栄養素が豊富に含まれています。
たとえば、水溶性食物繊維は、糖質の吸収を遅らせて血糖値上昇を抑える効果のある栄養素の代表例です。
食物繊維以外では、β-クリプトキサンチンとβ-カロテンも糖尿病予防効果が期待できます。
β-クリプトキサンチンやβ-カロテンは、高い抗酸化作用をもつカロテノイドに分類される栄養素です。
みかんに含まれる栄養素の中には、血糖値の上昇を抑え糖尿病予防に効果のあるものが豊富に含まれています。
みかんの果実のみでなく薄皮などにも豊富な栄養素が含まれる
みかんには、果実のみでなく薄皮の部分などにも豊富な栄養素が含まれています。
たとえば、食物繊維が薄皮や白い筋の部分に豊富に含まれているのは前述のとおりです。
他には、ビタミンCやヘスペリジンなどの抗酸化作用をもつ栄養素も豊富に含まれています。
天日干しをして乾燥させたみかんの皮は陳皮と呼ばれ、お茶やスパイスとして活用できます。
皮を煮詰めてジャムやマーマレードにしたり、細く刻んで冷凍させたものをお浸しのトッピングにするなどの活用方法があります。
皮の部分も栄養素が高く、工夫次第で日常生活に取り入れられるため、積極的に活用しましょう。
他の果物と比較してもみかんは血糖値管理に効果がある
みかんは、他の果物と比較しても血糖値管理における高い効果が期待できます。
前述のとおり、みかんは比較的GI値が低い果物です。
バナナやブドウのGI値は50を超えているのに対し、みかんは33となっており血糖値の上昇が遅い食品に分類されています。
果物の中では糖質量が少ない点や、β-クリプトキサンチンやβ-カロテンといった抗酸化作用のある栄養素を含んでいる点も、他の果物にはないみかんの魅力です。
さらに、みかんに豊富に含まれるクエン酸の作用により、エネルギー代謝が促進される効果も注目されています。
みかんは、果物の中でも血糖値管理において利点の多い食材です。
血糖値管理の観点から考えたみかんの食べ方のポイントを押さえよう

みかんは、血糖値管理に効果のある栄養素を豊富に含んでいる果物です。
血糖値の上昇に悩む人でも、みかんを上手に取り入れると糖尿病予防の効果が得られます。
しかし、みかんには一定の糖質が含まれているのも事実です。
血糖値管理効果があるからといって、多量に摂取すればよいというわけではありません。
健康管理のため、効果的なみかんの食べ方に配慮するのが大切です。
血糖値管理の観点から考えた、みかんの食べ方のポイントを以下に3点紹介します。
- 糖質の摂取過剰にならないよう1日に食べる量を守る
- みかんを食べる時間帯やタイミングにも配慮する
- みかんと他の果物の組み合わせ方にも配慮が必要
みかんを上手に食生活に取り入れて、効果的に血糖値管理を行いましょう。
糖質の摂取過剰にならないよう1日に食べる量を守る
みかんを食べる際は、糖質の摂取過剰にならないように1日に食べる量を守るのが大切です。
みかんは、果物の中では糖質量が少ない点を説明しましたが、大量に摂取すると糖質過多となってしまう恐れがあります。
特に冬場はスーパーで手軽に購入できるため、常に自宅にストックがあり無意識に食べ過ぎてしまう人もいるかもしれません。
みかんを食べ過ぎると、糖質過多となって血糖値の上昇につながるのみでなく、食物繊維の過多によって腹痛や下痢などの症状にもつながります。
一般的に、みかんは1日に2個までを目安として、食べ過ぎを避ける必要があります。
健康上利点の多いみかんですが、食べ過ぎると逆効果であるため、摂取量を守って食生活に取り入れてください。
ジュースなど糖質の多い状態での摂取は避けるのが無難
ジュースなど、糖質が多い状態での摂取は、血糖値管理においては避けたほうが無難です。
スーパーなどではオレンジジュースや缶詰などみかんの果肉を利用したさまざまな製品が販売されていますが、一般的に加工した食材は砂糖を加えるなど糖質が多い状態で販売されています。
血糖値の管理を適正に行いたい人や、糖尿病予防を重視したい人は、みかんを利用した加工品の摂取は控えたほうがよいでしょう。
みかんを食べる時間帯やタイミングにも配慮する

みかんを食べる際は、時間帯やタイミングにも配慮するのがよいです。
基本的には、血糖値が安定している時間帯やタイミングで食べるのがよいでしょう。
たとえば、昼食と夕食の間におやつとして食べたり、朝食のタイミングに合わせて食べたりするのが理想的です。
夕食後など、血糖値が高い状況でみかんを食べると、さらに糖質を摂取して急激な血糖値上昇を招いてしまいかねません。
みかんを食べる時間帯に加え、食べる量にも配慮する必要があります。
1日当たり最大でも2個までと上限を決めておき、それ以上食べないようにするのが大切です。
みかんは手軽に手に入る果物であるため、気が付けば手に取ってしまうという人もいるかもしれません。
みかんを食べる際は、時間帯や食べる量を気にしながら、摂り過ぎにならないように配慮してください。
みかんと他の果物の組み合わせ方にも配慮が必要
みかんと他の果物を組み合わせた献立を用意する際にも、配慮が必要です。
果物を食べ過ぎると、糖質過多になってしまう恐れがあります。
みかん自体は果物の中でも糖質量が少ないですが、他の果物の中には多量に糖質を含んでいるものもあるため、組み合わせに留意する必要があります。
果物の盛り合わせなど、果物を組み合わせた献立は見た目が華やかになり好まれますが、血糖値管理の側面で考えるとリスクが大きいため量や取り入れる種類に配慮する必要があります。
みかんは血糖値上昇や糖尿病にとって敵という誤解を解消しよう

糖尿病に悩んでいる人や、血糖値上昇を抑えたいと考える人にとって、みかんは血糖値を上げる敵であると認識しているケースも多いのではないでしょうか。
しかし、前述のとおり、みかんは血糖値上昇を抑える効果をもつ食材です。
みかんを上手に食生活に取り入れると、血糖値管理における味方となってくれるでしょう。
一方で、食べ方次第では糖質過多となってしまう恐れもある点は理解しておく必要があります。
みかんが血糖値管理における敵であるという認識が誤解であると説明するため、以下の3つの視点で紹介します。
- 果物は糖質が多いから血糖値に悪いというのは思い込み
- 工夫によって好きな果物をあきらめない食生活を実現できる
- みかんと他の果物を組み合わせた血糖値上昇を抑える食生活の具体例
今回の記事を参考にして、ぜひみかんに対する正しい理解を深めてみてください。
果物は糖質が多いから血糖値に悪いというのは思い込み
みかんをはじめとした果物には、多くの糖質が含まれているため、血糖値上昇に悪影響を及ぼすという認識は思い込みといえます。
確かに、果物は甘味があり糖質を含んだ食材です。
果物を多量に食べ続けると、血糖値上昇を招き糖尿病のリスクが高まるのは間違いありません。
しかし、みかんは糖質を含んだ食材であるとともに、多くの血糖値管理に効能がある栄養素を豊富に含んだ食材です。
糖質の吸収を遅らせる食物繊維や、高い抗酸化作用をもつカロテノイドなど、血糖値上昇を抑える作用がある栄養素が豊富に含まれています。
みかんは、果物の中でGI値が低い食材としても知られています。
甘味の強い果物だからといって、みかんが血糖値に悪いという認識は、ぜひ改めてください。
工夫によって好きな果物をあきらめない食生活を実現できる

みかんを食べる際に工夫をすると、好きな果物を我慢せず希望通りの食生活を実現できます。
糖尿病予防や血糖値上昇抑制などが必要な状況においても、自分の好きなものを食べて食生活を充実させたいと考える人も多いのではないでしょうか。
みかんが好きな人も、糖尿病だからとあきらめるのではなく、食生活に上手に取り入れていきましょう。
血糖値管理を優先する中では、1日に1個あるいは多くて2個までと上限量を定め、みかんの摂取量を守ります。
しっかりと噛んで食べると、みかん本来の甘味をしっかりと感じられます。
血糖値の上昇を抑えるため、食後に食べるのは避けて間食に用いるのも重要です。
決めたルールを守り食べ方に工夫をするなどして、みかんを上手に食生活に取り入れてください。
みかんと他の果物を組み合わせた血糖値上昇を抑える食生活の具体例
みかんと他の果物や食材と組み合わせて、血糖値上昇を抑制する献立を用意してはいかがでしょうか。
みかんは、他の食材と組み合わせてさらにおいしく活用できる食材の1つです。
特に他の果物との相性がよいため、糖質量や他の栄養素のバランスを考慮しながら、上手に取り入れていきましょう。
さらに、食物繊維が豊富なりんごと組み合わせるのも適しています。
以上の食材をヨーグルトと一緒に食べると、さまざまな果物の味わいが楽しめるフルーツヨーグルトとなります。
ヨーグルトに含まれるたんぱく質や脂質により、栄養バランスが整うのも魅力です。
みかんが好きな人は、他の食材とのバランスを考慮して、上手に食卓に取り入れてみてください。
血糖値を安定させるためには専門医への相談と連携が有効
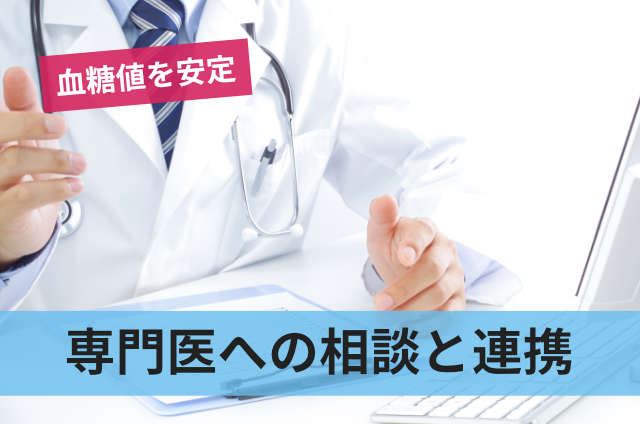
みかんは、血糖値管理に効果が高い食材ですが、正しい分量を守って日々の食事に取り入れる必要があります。
みかんに限らず、血糖値を管理するうえでは食事への配慮が必要不可欠です。
食事療法など、場合によっては専門的な判断を要する場面もあるため、血糖値管理をして糖尿病予防や治療をする際は内科あるいは糖尿病専門の医師に相談するのがよいでしょう。
血糖値を安定させるために専門医に相談するポイントとして、以下に2点紹介します。
- 血糖値が高い場合には専門医への相談を早めに行おう
- 効果的な食事療法を継続して行うために専門医の支援を受ける
血糖値が上昇傾向にある人や、糖尿病の予兆が現れた人は、早めに医療機関を受診しましょう。
血糖値が高い場合には専門医への相談を早めに行おう
血糖値が高いと判断された場合は、早めに専門医に相談するのがよいでしょう。
血糖値上昇は、さまざまな要因が影響している可能性があります。
単にみかんなど血糖値上昇を抑える効果のある食材を取り入れるのみでは、効果的な対策にならないかもしれません。
糖尿病にすでに罹患している可能性も踏まえ、早めに相談して対策を講じるようにします。
場合によっては、投薬などすぐに治療に取り掛かる必要がある可能性もあります。
通常よりも血糖値が高いと判断された場合は、かかりつけの医師あるいは最寄りの専門医に相談してみてください。
効果的な食事療法を継続して行うために専門医の支援を受ける
血糖値の適正な管理および糖尿病治療には、専門医の支援が欠かせません。
効果的な食事療法などの治療を継続して、血糖値の改善を図る必要があります。
食べてよいものや摂取を避けたほうがよいものなど、明確に示されるでしょう。
その中で、たとえばみかんが好きなので食べてもよいか、といった相談も可能です。
適正な分量を守って食べるのは問題ないなど、現状の体調を踏まえて適切な回答が得られます。
食事療法に加えて、血糖値管理に有効な運動療法など、患者1人ひとりの状況に適した対処方法が提示されます。
血糖値を適正に管理し糖尿病予防および治療をするために、信頼できる専門医の支援を受けてください。
みかんは血糖値管理以外にも積極的に取り入れる利点が多い果物

みかんは、血糖値管理において有効な食材です。
しかし、みかんは血糖値の上昇を抑える効果以外にも、健康上の利点が数多くあります。
果物の中で、容易に手に入れられる食材でもあるため、無理なく日々の生活に取り入られるのも利点です。
みかんの健康上の利点を理解して、積極的に日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
みかんがもつ血糖値管理以外の利点について、以下の2点を紹介します。
- 栄養素が豊富でさまざまな健康上の効用をもたらす
- 冬に広く出回り手軽に手に入るため継続して楽しめる
血糖値管理の目的に加え、みかんがもつ他の健康上の利点を同時に活用しましょう。
栄養素が豊富でさまざまな健康上の効用をもたらす
みかんは、さまざまな栄養素を豊富に含んでおり、健康上の効用をもたらす食材です。
血糖値上昇抑制効果を発揮する栄養素としては、前述のとおり食物繊維やβ-クリプトキサンチンおよびβ-カロテンなどが挙げられます。
他にも、みかんには以下のような栄養素があります。
- ビタミンC:免疫力を高め風邪などの感染症を予防する
- カリウム:体内の水分および塩分量を調整し高血圧を予防する
- ヘスペリジン:血流を促進し血圧の上昇を抑制する
食物繊維やヘスペリジンなど、果実でなく薄皮や白い筋の部分にも多くの栄養素が含まれているため、可能な範囲で食べるとよいでしょう。
みかんは、血糖値管理以外でも多くの健康効果が期待できるため、日常生活に積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
秋から晩冬に広く出回り手軽に手に入るため継続して楽しめる
みかんは、秋の早い段階から冬場の遅い時期まで広く市場に出回り、スーパーなど店舗で手軽に手に入るため、継続して楽しめる点も特徴です。
みかんは基本的には冬場に旬を迎える果物ですが、近年は早ければ秋の初旬から、遅いものでは3月頃にも出回っています。
ふるさと納税の返礼品にみかんを用意している自治体も多いため、上手に活用すると費用の負担も抑えられます。
みかん好きの人の中には、常に自宅にストックしているという人もいるのではないでしょうか。
血糖値管理をはじめとした健康維持を目的にして、比較的容易に手に入るみかんを継続して食べるのもよいでしょう。
みかんと血糖値の関係を理解し健康的な食生活を続けよう
みかんは、甘味がありおいしい果物であるため、糖質を多く含んでおり血糖値管理上は避けるほうがよい食材と考えている人もいるかもしれません。
しかし、実際はみかんには血糖値を適切に管理する効果をもつ栄養素が豊富に含まれています。
みかんは、食べ過ぎに注意して摂取する分量を守ると、急激な血糖値上昇を抑え糖尿病予防に効果がある食材です。
人によっては取り除いて食べる部分かもしれませんが、可能な限り食べたほうが栄養の面では利点があります。
みかんには血糖値管理以外にも健康上の利点が多いため、定期的に取り入れるとよいでしょう。
今回の記事を参考にして、ぜひみかんを上手に食事に取り入れてみてください。