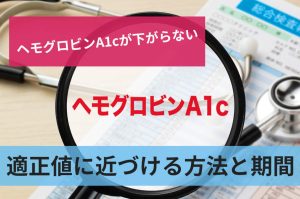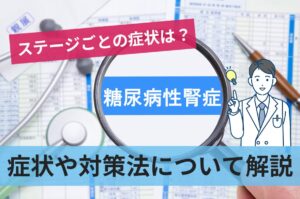HbA1cと血糖値は、糖尿病を管理する上で欠かせない重要な指標の1つです。
HbA1cと血糖値の適切なコントロールにより、糖尿病によるさらなる合併症を予防できます。
この記事では、HbA1cと血糖値のどちらが重要かを糖尿病の観点から徹底考察します。
- HbA1cと血糖値の特徴や違い
- 糖尿病管理におけるHbA1cと血糖値の重要性
- HbA1cと血糖値の効果的なコントロール方法
HbA1cと血糖値の特徴や役割から、糖尿病をより効果的に管理する方法を具体的に紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
HbA1cと血糖値はそれぞれ何を示すのかを理解する
ヘモグロビンに血液中のブドウ糖が結合すると、糖化ヘモグロビンになります。
HbA1cは、過去1〜2か月間の平均血糖値を反映するため、血液検査当日の食事や運動などの影響を受けません。
一方で血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことで、食事や運動などの様々な影響を受けるのが特徴です。
食事をすると、食べ物に含まれる炭水化物は分解されてブドウ糖になります。
分解されたブドウ糖は、小腸から吸収されてエネルギー源として血液により全身に運ばれます。
体内でブドウ糖の供給と消費が繰り返されるため、血糖値はある一定の範囲内に維持されます。
糖尿病の管理においてHbA1cと血糖値の役割はどう違うのかを理解する

血糖値は、日常生活で行われる運動や食事、ストレスなどの様々な影響を受けて常に変動しています。
HbA1cは、過去1〜2か月間の平均血糖値を反映するため、血液採血時より1〜2か月間前の血糖値の変動状況を把握するのに役立ちます。
そのため、糖尿病の管理における血糖自己測定時に血糖値が正常値であっても、測定時以外は正常であるか分かりません。
こうした血糖自己測定時以外の血糖状況は、HbA1cから把握できます。
ただしHbA1cからすべての血糖状況を把握できるわけではないため、血糖値の測定を併せて行うのが大切です。
HbA1cと血糖値の役割を理解して、より効果的な糖尿病の管理をしましょう。
HbA1cが血糖コントロールの長期的な指標となる
HbA1cは、過去1〜2か月間の平均血糖値を反映するため、血液採血時より1〜2か月間前の血糖コントロールの状況を把握できます。
HbA1cは長期的な指標であるため、生活習慣を改善したからといってすぐには反映されません。
食事や運動による生活習慣の改善を行っても、HbA1cを下げるには、少なくとも2か月は必要とされています。
HbA1cが高いと、糖尿病による三大合併症や心血管疾患などの合併症を引き起こすリスクが高まります。
糖尿病によるさらなる合併症を予防するためにも、継続的な生活習慣改善が最も大切です。
血糖値が日々の食事や運動の影響を反映する重要な指標である
血糖値は、日々の食事や運動、ストレスなどの様々な影響を受けて常に変動しています。
こうした1日の血糖値の変動状況は、血糖値の測定により把握が可能です。
血糖値の変動状況を自身で把握できる方法として、血糖自己測定があります。
さらに自身の低血糖を早期に把握できれば、低血糖による重篤化を予防できます。
ただし糖尿病の状態や治療方法、生活スタイルによって自己測定の回数やタイミングは人それぞれ異なります。
そのため、必ず医師に相談してから血糖自己測定を行いましょう。
継続的な血糖自己測定により、自身の血糖値を予測できるようになると、より効果的な血糖コントロールが可能になります。
糖尿病によるさらなる合併症を予防するためにも、HbA1cとともに血糖値の把握が大切となります。
HbA1cと血糖値の両方を重視して糖尿病を効果的に管理する

血糖値は、血糖測定時前から生活習慣を改善すれば、一時的に正常値になります。
しかし、血糖測定終了後に生活習慣の改善をやめてしまうと、HbA1cは高い結果になります。
つまり、血糖値は一時的に正常値で良好のようでも、長期的な指標であるHbA1cは継続して高い状態であり良好とはいえないということです。
一方でHbA1cが良好であっても、今まで継続していた食事や運動習慣の改善をやめてしまうと、気づかないうちに血糖値が急上昇している可能性があります。
血糖値の上昇を抑えられると、HbA1cは連動して低下します。
糖尿病を効果的に管理するには、HbA1cと血糖値をともに重視していくのが大切です。
HbA1cと血糖値をともに下げて良好な血糖コントロールをしていくためには、継続的な生活習慣の改善が必要となります。
今までの食事を少し工夫したり、運動を取り入れたりするのみでHbA1cと血糖値を下げられる効果が期待できます。
そのため、自分のできる無理のない範囲で意識的に取り入れてみましょう。
規則正しい食事はHbA1cと血糖値を低下させる
食事の間隔を空けると、血糖値を下げる時間が確保できて血糖値が安定します。
ただし食事の間隔が長くなると、次の食事後に血糖値が急上昇する可能性があります。
そのため、食事は1日3食を基本として、可能な限り4〜5時間の均等間隔を空けて摂取するのが理想的です。
他にも朝食を食べないと、肝臓のインスリンを分泌する機能が低下します。
インスリンを分泌する機能が回復するまでには時間がかかるため、インスリンの作用が低下して昼食や夕食後の血糖値が急上昇します。
特にインスリンの分泌は、午前中が活発な状態です。
そのため、可能な限り早い時間帯に朝食を摂取すると、血糖値の急上昇を抑制できます。
さらに夕食の時間が遅いと、メラトニンの分泌が増えてインスリンの分泌が抑制されます。
HbA1cは血糖値と連動して徐々に下がっていくため、規則正しい食事を継続するのが大切です。
食事はゆっくりとよく噛んで食べよう
ゆっくりよく噛んで食べると、小腸からの糖質の吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を抑制できます。
糖尿病の人が早食いをすると、血糖値の急上昇にインスリンの分泌が間に合いません。
そのため満腹を感じる前に食べてしまい、過食につながります。
過食により肥満になると、蓄積された内臓脂肪によりインスリンの働きが低下して、さらに血糖値が上昇する恐れがあります。
こうした過食による肥満は、ゆっくりよく嚙んで食べる食事により予防が可能です。
よく嚙んで食べる食事は、満腹中枢が働いて過食を避けられるため、肥満予防につながります。
肥満が解消されて血糖値が安定すると、HbA1cも低下します。
ゆっくりよく噛んで食べるために、以下のような工夫をしてみましょう。
- ひと口の量を減らす
- 食事の時間に余裕を持つ
- 食事に集中する
- 噛む回数を意識する
- こんにゃくやごぼうなどの歯ごたえのある食材を取り入れる
- 食材は大きめに切る
- 薄味にする
- 可能な限り外食を避ける
- 咀嚼し終わってから、次の食べ物を口に入れる
- 煮物よりも焼き魚や生魚を食べる
ゆっくりよく噛んで食べると血糖値が安定するのみでなく、虫歯予防や胃腸の働きを活発にする効果もあるため、意識的に取り組んでください。
食物繊維が豊富な食品にはHbA1cと血糖値を下げる効果がある

食物繊維は、小腸からのブドウ糖の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を抑制します。
食物繊維は意識して摂取しないと、摂取量が不足する場合が多いため、以下のような食物繊維を多く含む食品を意識的に摂取しましょう。
- 野菜(かぼちゃやモロヘイヤ)
- 果物(いちごやバナナ)
- 全粒穀物(玄米やライ麦パン)
- 豆類(大豆やいんげん豆)
- 海藻類(ひじきやきくらげ)
- ナッツ(カシューナッツやマカダミアナッツ)
- きのこ類(まいたけやエリンギ)
- イモ類(里芋や山芋)
さらに朝食でたんぱく質とともに食物繊維を摂取すると、血糖値の上昇を抑えられます。
血糖値の上昇を抑制できると、HbA1cも連動して低下する効果が期待できます。
他にも食物繊維には腸内環境を整えたり、生活習慣病を予防したりする効果があるため、積極的に摂取してください。
低糖質食品や低GI食品の活用により血糖値の急上昇を予防する
糖質を多く含む食品を低糖質食品や低GI食品に置き換えると、血糖値の上昇を予防できます。
低糖質食品を活用すると、血糖値に大きな影響を与える糖質を手軽に抑えられます。
そのため、血糖値の上昇は緩やかになります。
一方で低GI食品とは、血糖値の上昇速度を表すGI値が55以下の食品のことです。
低GI食品は、糖質が体内で消化吸収されるまでに時間がかかるため、食後血糖値の上昇を緩やかにする効果をもちます。
適切な血糖コントロールには、糖質量を意識したバランスの良い食生活が必要となります。
以下のような低糖質食品や低GI食品を活用して、適量の糖質摂取を心がけましょう。
低糖質食品
- そばやうどん
- 肉類(鶏むね肉や豚バラ肉)
- 魚類(鮭やたら)
- いも類(里芋や山芋)
- 乳製品(ヨーグルトや牛乳)
- 葉物野菜(ほうれん草や小松菜)
- 豆類(木綿豆腐やがんもどき)
- 卵
- 果物(いちごやグレープフルーツ)
- 菓子(ハイカカオチョコレートやナッツ)
低GI食品
- 果物(りんごやいちご)
- 海藻類
- 大豆食品
- そばやスパゲッティ
- きのこ類
- ライ麦パン
低糖質食品や低GI食品に置き換えて血糖値の上昇を抑制できると、HbA1cも連動して下がります。
ただし糖質は体を動かすエネルギーであるため、過剰な糖質制限をすると健康に悪影響を及ぼします。
そのため、必ず適量摂取をするように心がけてください。
定期的な運動はHbA1cと血糖値を低下させる効果をもつ

運動には、HbA1cと血糖値を低下させる効果があります。
毎日30分以上または週180分以上を目安に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を行うのが理想的です。
さらに有酸素運動とともに筋力トレーニングを組み合わせて行うと、血糖値を低下させる効果がさらに高まります。
特に、足や背中などの大きな筋肉を中心とした筋力トレーニングが効果的です。
ただし強度の高い運動は、身体にエネルギーを補充しようとして血糖値を上げるホルモンが多く分泌されます。
一時的に血糖値が高い状態となる場合があるため、中等度の運動を意識してください。
そのため、無理のない範囲で自分に合った運動を継続的に行いましょう。
血糖値を安定させてHbA1cを下げるためにも、継続的な運動が最も大切です。
ストレッチやヨガはストレスを解消してHbA1cと血糖値を改善する
ストレッチやヨガを継続的に行うと、ストレスを解消してHbA1cと血糖値の改善につながります。
ストレスが溜まり続けると、インスリンの感受性が低下して血糖コントロールが困難になります。
ゆったりとした呼吸法で行うストレッチやヨガは、筋肉の緊張をほぐしたり、心をリラックスさせたりしてストレス解消に効果的です。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動とストレッチやヨガを組み合わせると、HbA1cと血糖値を下げる効果がより期待できます。
そのため、リラックスできる程度のストレッチやヨガを日常の運動に取り入れてみましょう。
HbA1cの変化が血糖値のコントロール状況を正確に反映するとは限らない

HbA1cは、過去1〜2か月間の平均血糖値を示しているため、1日の血糖値の変動状況は確認できません。
血糖値の上昇と低下が急な人と穏やかな人では、血糖値の変動に大きな差がありますが、HbA1cは同じ数値になります。
HbA1cが安定していても、食後に血糖値が急上昇して急降下する血糖値スパイクが起こっていると、血管にダメージを与えます。
こうした状態が続くと、糖尿病によるさらなる合併症を引き起こすリスクも高まるため、HbA1cの欠点を理解して適宜自身で血糖測定するのが重要です。
糖尿病管理において正確に自身の血糖値の状態を把握するためにも、HbA1cのみでなく血糖値も意識しましょう。
HbA1cと血糖値のどちらを重視すべきかは状況によって異なる
HbA1cと血糖値のどちらを重視するかは、個々の状況に応じて判断する必要があります。
糖尿病の管理におけるHbA1cの目標値は一般的に6〜7%とされていますが、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。
HbA1cの目標値は、年齢や血糖コントロールの状況、合併症の有無などにより異なります。
65歳未満の一般成人のHbA1cの目標値は、以下の通りです。
- 血糖値の正常化を目指している場合:HbA1c値 6.0%未満
- 糖尿病合併症予防を目指している場合:HbA1c値 7.0%未満
- 治療強化が困難な場合:HbA1c値 8.0%未満
一般的な糖尿病の管理においては、HbA1cの目標値を7.0%未満とするのがほとんどです。
ただし年齢が若い人や糖尿病と診断されて間もない人は、HbA1c値6.0%未満を目標とするケースもあります。
65歳以上の高齢者のHbA1cの目標値は、7.0〜8.5%未満が目安です。
高齢者は一般成人と比較して、以下の2つのリスクが伴います。
- 低血糖を引き起こして重篤化する
- 併発疾患により心筋梗塞や脳卒中などのさらなる合併症を引き起こす
上記のリスクを避けるために、高齢者のHbA1cの目標値は一般成人よりも高く設定されています。
一方で以下のような人には、血糖自己測定による血糖管理が有効です。
- インスリン療法を行っている人
- 低血糖を頻繁に起こす人
- 糖尿病で妊娠希望の人
インスリン療法を行っている人は、血糖自己測定で自身の血糖値を把握してから規定の範囲内でインスリンの注射量を調整する必要があります。
血糖自己測定で血糖値をリアルタイムで把握できると、より効果的な血糖コントロールができます。
さらに低血糖を頻繁に起こす人は、血糖自己測定により低血糖を把握できるため、速やかな対応が可能です。
上記のように、自身の状況によってHbA1cと血糖値のどちらを重視するかは異なるため、必ず医師と相談してから適切な管理を行いましょう。
HbA1cと血糖値の違いを理解して適切なバランスによる管理を行う

HbA1cと血糖値はどちらも血糖値を示す指標ですが、それぞれで役割や特徴が異なります。
糖尿病の管理において血糖値をより効果的にコントロールするためには、HbA1cと血糖値の両方を重視しなければなりません。
今までの生活を大きく変えなくとも、少しの工夫でHbA1cと血糖値を下げる効果が期待できます。
糖尿病であっても継続的な生活習慣の改善により、健康な人とほとんど変わらない生活が可能です。
そのため、初めに過度なストレスがかからない程度から食事の工夫や運動を取り入れてみましょう。