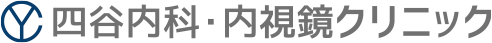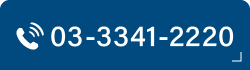慢性胃炎は、長期間にわたって胃の粘膜に炎症が続く病気です。現代社会では胃の不快感を訴える人は多い一方、慢性胃炎は病理学的に診断される状態で、無症状のまま見つかることもあります。特にピロリ菌感染や生活習慣の乱れが関与することが多く、放置すると胃潰瘍や胃がんへ進展する可能性もあるため、早めの対処が大切です。
この記事では、慢性胃炎の原因・症状・治療法・予防法を、わかりやすく徹底解説していきます。
慢性胃炎とは何か
 慢性胃炎とは、胃の粘膜に長期間にわたって炎症が持続している状態を指します。通常、胃は強い酸(胃酸)を分泌しながらも、自らの粘膜を保護する仕組みを備えています。しかし、このバランスが崩れると胃粘膜が傷つき、炎症が長引いてしまいます。
慢性胃炎とは、胃の粘膜に長期間にわたって炎症が持続している状態を指します。通常、胃は強い酸(胃酸)を分泌しながらも、自らの粘膜を保護する仕組みを備えています。しかし、このバランスが崩れると胃粘膜が傷つき、炎症が長引いてしまいます。
胃炎という病名は比較的耳にすることが多いものの、実際に「慢性胃炎」と診断された場合には、急性胃炎とは異なる病態やリスクが潜んでいるため注意が必要です。慢性胃炎は進行がゆるやかで、自覚症状が乏しいケースも多いですが、放置すると萎縮性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスクへとつながる可能性もあります。
①急性胃炎との違い
慢性胃炎と急性胃炎は似ているようで、その性質は大きく異なります。
- 急性胃炎:一時的な要因(暴飲暴食、薬剤、強いストレスなど)で胃粘膜が炎症を起こすもの。症状は数日から数週間で治まることが多い。
- 慢性胃炎:数か月から数年にわたり炎症が持続する。ピロリ菌感染や長期的な生活習慣の乱れが主因であり、胃粘膜が徐々に傷み、回復しづらい状態になる。
つまり、急性胃炎は「一過性」、慢性胃炎は「持続性」という違いがポイントです。
②胃粘膜に起こる変化
慢性胃炎が進行すると、胃の中で以下のような変化が起こります。
- 粘膜の損傷:炎症が繰り返されることで、胃粘膜の細胞がダメージを受ける。
- 防御機能の低下:本来、胃は胃酸から自らを守るバリア機能を持つが、慢性炎症によりその力が弱まる。
- 萎縮性胃炎の発症:粘膜が薄くなり、胃酸や消化酵素の分泌が減少。消化不良や栄養吸収障害の原因となる。
- 腸上皮化生:胃粘膜が腸の粘膜のような細胞に置き換わる変化。これは前がん病変とも呼ばれ、将来的に胃がんリスクを高める。
このように、慢性胃炎は単なる胃の不調ではなく、長期的に胃の健康を脅かす病気なのです。
③なぜ慢性胃炎が重要視されるのか
近年、慢性胃炎が注目されるのは、単なる胃の不快感にとどまらず、将来的な疾患リスクにつながるためです。特に日本では胃がんの発症率が高く、その背景にはピロリ菌感染による慢性胃炎の広がりが関与しています。
また、慢性胃炎は症状が軽度な場合や無症状で経過することもあり、「なんとなく胃が重い」「疲れると胃が痛む」といった小さなサインを見逃しやすいのが特徴です。そのため、検診や内視鏡で偶然発見されるケースも少なくありません。
慢性胃炎の主な原因
慢性胃炎の発症には、さまざまな要因が複雑に関与しています。代表的なものを一つずつ見ていきましょう。
①ピロリ菌感染
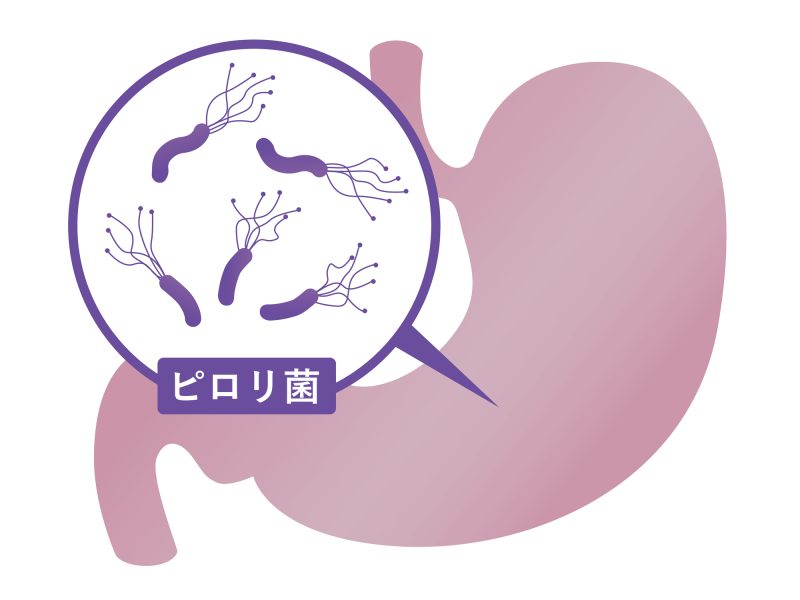 最も重要な原因はヘリコバクター・ピロリ菌(通称ピロリ菌)の感染です。この菌は胃酸に強く、長期間胃の中に住み続け、粘膜を慢性的に刺激します。感染者は胃のバリア機能が弱まり、炎症が続きやすくなります。
最も重要な原因はヘリコバクター・ピロリ菌(通称ピロリ菌)の感染です。この菌は胃酸に強く、長期間胃の中に住み続け、粘膜を慢性的に刺激します。感染者は胃のバリア機能が弱まり、炎症が続きやすくなります。
特に日本ではピロリ菌感染率については、1950年生まれ前後で約60%台、1990年台で15%前後、2000年台で1桁台と推定されており。50代以上でも40–60%と幅があります。慢性胃炎から胃がんに進展する大きなリスク要因とされています。
②食生活の乱れ

- アルコールの過剰摂取
- 脂っこい食事
- 辛い香辛料や刺激の強い食材
これらは胃酸の分泌を過剰に促したり、粘膜を直接刺激したりすることで胃炎を悪化させます。
③薬剤の影響
解熱鎮痛薬(NSAIDs)は明確なリスクとなりえます。またステロイド単独の潰瘍リスクは限定的ですが、NSAIDs併用で相乗的に上がります。特に高齢者や持病で薬を常用する人は注意が必要です。
④ストレスや生活習慣
精神的ストレスや不規則な生活は、自律神経を乱し胃酸分泌をコントロールできなくなります。その結果、胃粘膜が傷つき炎症が長引きます。
⑤加齢による変化
年齢とともに胃の粘膜は萎縮しやすくなり、胃酸の分泌も低下します。これが慢性胃炎の温床となります。
慢性胃炎の代表的な症状
 慢性胃炎は進行の仕方や原因によって症状の出方が異なり、一人ひとりの体験は大きく変わります。典型的には「胃が重い」「食べたあとにすっきりしない」といった不快感から始まりますが、症状の強さは日によっても変動しやすく、疲労やストレスで悪化する人も少なくありません。
慢性胃炎は進行の仕方や原因によって症状の出方が異なり、一人ひとりの体験は大きく変わります。典型的には「胃が重い」「食べたあとにすっきりしない」といった不快感から始まりますが、症状の強さは日によっても変動しやすく、疲労やストレスで悪化する人も少なくありません。
まず多くの患者が訴えるのは胃もたれや膨満感です。食後に胃の中に食べ物が長く残っているような感覚があり、胃が張って苦しい、ゲップが多いといった症状を伴うこともあります。消化が遅れている感覚は生活の質を大きく下げ、外食や人付き合いを避ける原因にもなります。
次に目立つのが吐き気や嘔吐です。慢性胃炎では胃酸分泌のバランスが崩れていることが多く、空腹時に気持ち悪くなる場合や、食べ過ぎたあとに吐き気を感じる場合があります。嘔吐まで至るのはまれですが、軽い吐き気が続くだけでも日常生活に大きなストレスを与えます。
また、胸やけや胃の痛みを訴える患者も多いです。胃酸が粘膜を刺激することで食道方向に逆流したり、炎症が痛みとして自覚されたりします。特に夜間に胸やけが強く、睡眠が妨げられる人もいます。
症状が長引くと食欲不振や体重減少につながります。少し食べただけで満腹感が強くなるため、食事量が自然と減り、栄養不足に陥ることもあります。慢性胃炎は進行が緩やかなため、知らず知らずのうちに体重が減っていることに気づくケースも少なくありません。
一方で、慢性胃炎は無症状で進行することも多いのが特徴です。健康診断や人間ドックの内視鏡検査で初めて発見される人もいます。「症状がない=問題ない」とは限らず、萎縮や腸上皮化生がすでに進行している場合もあるため、注意が必要です。
慢性胃炎の種類
慢性胃炎にはいくつかのタイプがあり、それぞれで病態や将来のリスクが異なります。
比較的軽い段階では表層性胃炎がみられます。これは胃粘膜の表面に炎症がとどまっている状態で、症状も胃の不快感や軽いもたれ感にとどまることが多いです。
進行すると萎縮性胃炎へと変化します。これは胃粘膜が薄くなり、胃酸や消化酵素の分泌が減少する状態です。消化能力が落ちるため慢性的な胃もたれが起こりやすくなり、さらに胃がんのリスクが高まることが知られています。
また、びらん性胃炎では粘膜がただれ、時に出血を伴います。内視鏡で小さな出血斑やびらんが見つかることがあり、黒色便(タール便)や吐血を起こす場合もあります。
さらに、化学性(反応性)胃症、いわゆる「逆流性胃炎」と呼ばれるものもあります。これは十二指腸から胆汁や消化液が胃に逆流して粘膜を刺激するもので、胃のむかつきや苦味を感じる症状が目立ちます。
慢性胃炎の診断方法
 慢性胃炎の診断は、問診と検査を組み合わせて行われます。まず医師は、日頃の食生活、アルコールや薬の使用歴、症状の出方や持続期間を丁寧に聞き取ります。この情報は診断の手がかりとなるだけでなく、治療計画を立てる上でも重要です。
慢性胃炎の診断は、問診と検査を組み合わせて行われます。まず医師は、日頃の食生活、アルコールや薬の使用歴、症状の出方や持続期間を丁寧に聞き取ります。この情報は診断の手がかりとなるだけでなく、治療計画を立てる上でも重要です。
次に行われるのが内視鏡検査です。胃カメラで直接粘膜を観察し、炎症の程度やびらん、出血の有無を確認します。さらに内視鏡の際に生検を行い、組織を顕微鏡で調べることもあります。萎縮や腸上皮化生の有無を確認することで、将来的なリスクを評価できます。
加えて、慢性胃炎の背景として重要なピロリ菌の検査が実施されます。尿素呼気試験、便中抗原検査、血液抗体検査などがあり、内視鏡時に迅速ウレアーゼ試験を行うこともあります。感染の有無を明らかにすることで、治療方針が大きく変わります。
慢性胃炎の治療法
治療は原因や症状の程度に応じて多様です。特にピロリ菌感染がある場合は、除菌療法が第一選択になります。日本では抗菌薬と胃酸を抑える薬を7日間服用する方法が標準であり、多くのケースで成功率は高いと報告されています。
除菌後も症状が残る場合や、ピロリ菌が関与していない慢性胃炎では、薬物療法が中心となります。胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカー、胃粘膜を守る薬などが用いられます。
さらに、食生活を整える食事療法は治療の基盤です。消化にやさしい食材を中心にとり、脂っこい料理や刺激物、過度の飲酒を避けることで症状の改善につながります。
漢方薬も一部では利用されており、特に「六君子湯」は食欲不振や胃もたれに対して有効性が報告されています。ただし、漢方は慢性胃炎そのものを治すのではなく、症状の緩和を目的とする補助的治療として位置づけるのが適切です。医師の処方に従ってください。
外科的治療は通常不要ですが、潰瘍の出血やポリープ、腫瘍などの合併症がある場合には、内視鏡的切除や手術が検討されることもあります。
慢性胃炎に効果的な
食事と生活習慣
 慢性胃炎の改善には、薬だけでなく日常の過ごし方が欠かせません。胃にやさしい食事の代表は、おかゆや雑炊、豆腐や白身魚などの消化しやすい食品です。温かいスープ類も胃を落ち着かせる効果があります。
慢性胃炎の改善には、薬だけでなく日常の過ごし方が欠かせません。胃にやさしい食事の代表は、おかゆや雑炊、豆腐や白身魚などの消化しやすい食品です。温かいスープ類も胃を落ち着かせる効果があります。
一方で、脂っこい揚げ物や唐辛子を多く使った料理、アルコールやコーヒーなどの嗜好品は、人によって症状を悪化させることがあります。ただし、全ての人に当てはまるわけではなく、自分の症状と結びつけて控える工夫が重要です。
また、食事のとり方も大切です。少量をゆっくりよく噛んで食べる、夜遅くの食事を避けるといった工夫で胃への負担は軽くなります。
さらに、睡眠不足や精神的ストレスも胃の状態に大きく影響します。十分な休養とリラックスできる時間を持つことは、薬に勝る治療効果を発揮する場合もあります。
放置するとどうなる?
慢性胃炎の合併症
 慢性胃炎を放置すると、粘膜の炎症が進行し、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。代表的なのが胃潰瘍で、これは粘膜の損傷が深く進み、強い痛みや出血を伴うことがあります。
慢性胃炎を放置すると、粘膜の炎症が進行し、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。代表的なのが胃潰瘍で、これは粘膜の損傷が深く進み、強い痛みや出血を伴うことがあります。
また、胃ポリープが発生することもあり、これは粘膜が炎症を繰り返す中で隆起性の病変を作るものです。多くは良性ですが、大きくなると出血の原因になったり、まれにがん化のリスクも考慮されます。
さらに見逃せないのが胃がんです。特に萎縮性胃炎や腸上皮化生が進んだ場合は、胃がんに移行するリスクが上昇します。無症状の慢性胃炎でも油断せず、定期的に医師のチェックを受けることが大切です。
慢性胃炎を予防する方法
予防の基本は日常生活の改善です。まず食生活を整え、胃に過度な負担をかけないことが大切です。脂っこい料理やアルコールを控え、規則正しい食習慣を意識することが予防につながります。
ストレスをためない生活も重要です。適度な運動や趣味の時間を持つことで自律神経が安定し、胃酸分泌のバランスも整います。
さらに、日本では胃がん検診が普及しており、50歳以上を対象に2年ごとの内視鏡検査やX線検査が推奨されています。リスクが高い人は医師の判断でより短い間隔での検査を受けることもあります。
慢性胃炎に関するよくある質問
慢性胃炎は完治しますか?
ピロリ菌が原因であれば、除菌によって炎症の進行を抑えられます。ただし萎縮や腸上皮化生が進んでいる場合、完全に元通りになるわけではありません。
ピロリ菌がいなくても胃炎になりますか?
はい。薬剤やストレス、食生活の乱れなど他の要因でも胃炎は起こります。
慢性胃炎でも食べやすい間食は?
消化が良いヨーグルトやバナナなどが比較的安全とされています。
サプリや健康食品は役立ちますか?
一部の乳酸菌サプリやプロバイオティクスは補助的に役立つ可能性がありますが、治療の中心はあくまで医師の指導です。
胃薬を長期間飲んで大丈夫ですか?
プロトンポンプ阻害薬などは長期使用で副作用リスクがあるため、医師の管理下で必要最小限の使用が望まれます。
胃炎と胃がんの違いは?
胃炎は粘膜の炎症で、胃がんは細胞が異常に増える悪性腫瘍です。慢性胃炎を放置すると胃がんリスクが高まる可能性があります。