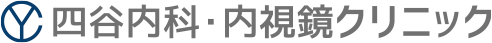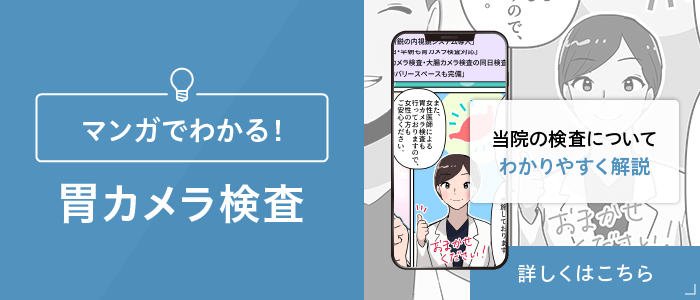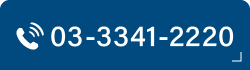このようなお悩みは
ありませんか?
- のどのつかえ感がある
- 食道に異物感がある
- 咳や喉の違和感がある
- のどのつかえ感とともに、胸やけや呑酸がある
- のどの違和感と共に、体重減少や食事摂取量の減少がある
上記のようなお悩みがある方は、好酸球性食道炎の可能性があります。好酸球性食道炎を放置してしまうと、食道が炎症によって狭くなってしまうといわれています。食道が狭くなると、食べられないなどの食生活に大きく関連してしまいます。些細な症状でも気になることがある方は、お気軽に当院までご相談ください。
好酸球性食道炎とは
 好酸球性食道炎(EoE)は、主に食物由来のアレルゲンに対する免疫反応によって食道内に炎症が慢性的に続く病気です。好酸球性食道炎による炎症が長期間にわたって続くことで、食道の動きが鈍くなったり、通過する道が狭まったりするため、「食べ物が喉を通りにくい」「つかえる感じがする」といった症状が起こることがあります。成人のつかえ感の原因として、近年注目されている疾患のひとつとなります。発症のピークは30〜40歳代に多く、特に男性に多くみられるのが特徴で、女性よりも2〜3倍の頻度で診断されています。また、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など、アレルギーに関わる他の病気を過去に持っているケースが全体の約7割に及び、アレルギー体質との関連が強く示唆されています。
好酸球性食道炎(EoE)は、主に食物由来のアレルゲンに対する免疫反応によって食道内に炎症が慢性的に続く病気です。好酸球性食道炎による炎症が長期間にわたって続くことで、食道の動きが鈍くなったり、通過する道が狭まったりするため、「食べ物が喉を通りにくい」「つかえる感じがする」といった症状が起こることがあります。成人のつかえ感の原因として、近年注目されている疾患のひとつとなります。発症のピークは30〜40歳代に多く、特に男性に多くみられるのが特徴で、女性よりも2〜3倍の頻度で診断されています。また、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など、アレルギーに関わる他の病気を過去に持っているケースが全体の約7割に及び、アレルギー体質との関連が強く示唆されています。
好酸球性胃腸炎との違い
好酸球性食道炎(EoE)と名前が似ている疾患に「好酸球性胃腸炎(EGE)」があります。好酸球性胃腸炎は食道に限らず胃や腸など消化管全体に炎症が及びます。一方で、好酸球性食道炎は病変が食道のみに限定される点が大きな違いとなります。そのため、好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎は別々の病態として分類されており、EoEがEGEや好酸球増多症に進展することは、現在のところ報告されていません。日本では、好酸球性食道炎が人間ドックや健康診断などの内視鏡検査で偶然見つかるケースが多いといわれています。自覚症状がほとんどないまま診断されることも珍しくなく、典型的な内視鏡所見がありながら無症状の人も少なくありません。放置すると食道の狭窄や固い食べ物の通過障害につながるおそれもあるため、早期発見と適切な管理が重要となります。
好酸球性胃腸炎(EGE)
好酸球性胃腸炎(EGE)は、胃や小腸、大腸などの消化管に好酸球が異常に集まり、慢性的な炎症を引き起こす疾患となります。好酸球性胃腸炎では、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの消化器症状が出現し、特に食後にみぞおち(心窩部)付近に強い痛みが現れることが特徴となります。この痛みは、一般的な胃薬や制酸薬では十分に改善しないことがあります。
EGEは、組織検査(生検)で顕著な好酸球の浸潤が確認されること、また血液検査で末梢血中の好酸球数が増加していることなどで総合的に診断することが可能となります。また症状がほとんど出ていない「無症候性好酸球性胃腸炎」も存在し、血液検査や組織所見からEGEが疑われたとしても、実際には自覚症状がないこともあります。胃に生じた好酸球性胃腸炎に対する内視鏡所見は特異的ではないとされていますが、過去の報告では、胃粘膜に斑状の脱色や「マスクメロン様」と呼ばれる独特な模様が見られた症例もあります
好酸球食道炎の原因
 好酸球性食道炎(EoE)は、遺伝的な体質を持つ人が、特定の食物に含まれるアレルゲンに繰り返しさらされることで、食道の粘膜に慢性の炎症が起こる病気となります。好酸球食道炎の炎症は、胃や腸ではなく、食道のみに限定される点が特徴となります。アレルゲンに対する過敏な免疫反応が発端ですが、食物そのものだけでなく、環境的な要因も発症に影響を与えていると考えられています。生まれてすぐの時期に抗生物質の投与を受けたり、帝王切開で出生したり、早産であったりといった出生時の環境要因が、免疫のバランスに影響してEoE発症の素地を作る可能性が示唆されています。さらに、近年ではピロリ菌の感染率が下がっていることも、免疫環境の変化を通じてEoEの増加と関連があるのではないかと指摘されています。しかし、実際にどの食物が原因となっているかを特定することは困難なことが多く、明確なアレルゲンが見つからないケースがほとんどです。
好酸球性食道炎(EoE)は、遺伝的な体質を持つ人が、特定の食物に含まれるアレルゲンに繰り返しさらされることで、食道の粘膜に慢性の炎症が起こる病気となります。好酸球食道炎の炎症は、胃や腸ではなく、食道のみに限定される点が特徴となります。アレルゲンに対する過敏な免疫反応が発端ですが、食物そのものだけでなく、環境的な要因も発症に影響を与えていると考えられています。生まれてすぐの時期に抗生物質の投与を受けたり、帝王切開で出生したり、早産であったりといった出生時の環境要因が、免疫のバランスに影響してEoE発症の素地を作る可能性が示唆されています。さらに、近年ではピロリ菌の感染率が下がっていることも、免疫環境の変化を通じてEoEの増加と関連があるのではないかと指摘されています。しかし、実際にどの食物が原因となっているかを特定することは困難なことが多く、明確なアレルゲンが見つからないケースがほとんどです。
また、EoEと胃酸の逆流による逆流性食道炎(GERD)との関係も注目されています。EoEによって食道の運動機能が低下すると胃酸が逆流しやすくなり、GERDを引き起こすことがあります。一方で、GERDによる酸による粘膜障害がアレルゲンの侵入を促し、結果としてEoEの発症に関与する可能性もあるため、両者は互いに影響し合っていると考えられています。EoEの発症は男性に多く、女性より約2倍の頻度で診断されており、性別によって異なる特徴のひとつと考えられています。
好酸球食道炎の症状
好酸球食道炎の代表的な症状は、食道内に異物がつかえているような「つかえ感」となります。特に成人で発症したケースでは、「食べ物が喉に引っかかる」「胸やのどが圧迫されるような感覚がある」と訴える人が多く見られます。ただし、実際に食べ物が通らなくなるほどの重度の狭窄がない限り、食事の通過が完全に妨げられることは少なく、吐き出すようなケースはそれほど頻繁ではありません。欧米では、こうした「つかえ感」などの症状を契機に内視鏡検査を受けた人のうち、2〜6割が好酸球食道炎と診断されたという報告もあり、食道の違和感の主要な原因のひとつともいわれいます。
一方で、内視鏡検査で好酸球食道炎に典型的な所見が見られたとしても、本人にまったく症状がない場合もあります。このような場合では、診断名として「好酸球性食道炎」と断定するのではなく、「無症候性好酸球食道炎」あるいは「食道好酸球増多」などと表現され、経過観察や慎重な診断が求められることもあります。
好酸球食道炎の診断方法
 好酸球性食道炎の診断は、患者様の症状や過去のアレルギー歴などの問診や症状が好酸球性食道炎を疑わせるものであれば、胃内視鏡検査(胃カメラ)を行う必要があります。
好酸球性食道炎の診断は、患者様の症状や過去のアレルギー歴などの問診や症状が好酸球性食道炎を疑わせるものであれば、胃内視鏡検査(胃カメラ)を行う必要があります。
胃内視鏡検査において、食道の粘膜に赤みや腫れ、白斑などの異常が見られることがある場合には組織検査を行う必要があります。また場合によっては、アレルギー検査や血液検査も行う場合もございます。
内視鏡検査で確認される
代表的な所見
- 白色の沈着物
- 食道の内腔にみられるリング状のくびれ
- 粘膜の腫れや浮腫による血管の見えにくさ
- 縦に走る溝のような模様
- 食道の狭窄や内腔の狭小化
すべての症例に明らかな異常が見られるわけではなく、約1割程度の患者様では、内視鏡上ほとんど異常が確認できないこともあります。そのため、目立った所見がない場合でも、特に下部食道の組織を採取して調べることも重要です。
胃カメラ検査
胃カメラ(内視鏡検査)は、胃や食道、十二指腸の内部を直接観察するための検査となります。細長い管の先端にカメラが取り付けられており、口または鼻から、食道を通って胃まで挿入し、内部の様子をリアルタイムでモニターに映し出します。胃カメラ検査は、胃痛や胸やけ、吐血、食道の異常などの症状を調べる際に用いられます。また、異常が見つかった場合には、組織の一部を採取して病理検査を行うことも可能です。検査は、鎮静剤を使用して行うことも可能であり、眠ったような状態で検査を受けることで痛みや不快感を最小限に抑えることも可能となります。
好酸球食道炎の治療方法
好酸球食道炎の治療には、原因となる食物を取り除く「除去食療法」が有効とされる一方で、現実にはその実施が難しいともいわれています。どの食物がアレルゲンになっているかを正確に突き止めるのは非常に困難であり、明確な原因食品が特定できるケースは限られています。そのため、好酸球食道炎の治療は薬物療法が中心となります。
薬物療法
胃酸の分泌を抑える薬(PPI=プロトンポンプ阻害薬やP-CAB=カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)を8週間使用します。胃酸の分泌を抑える薬により多くの患者様で症状や炎症の改善が得られるとされています。しかし、効果が不十分な場合には、ステロイドを用いた局所治療(嚥下による投与)を約12週間実施する場合もあります。ステロイド治療によって症状が改善した場合は、薬の量を減らしながら、長期的な維持治療を検討することが推奨されます。維持療法の有効性や適切な治療期間については、今のところ明確なエビデンスが少なく、「いつまで治療を続けるべきか」は個々の患者ごとに判断する必要があります。なお、薬をやめると再び症状が現れる例もあるため、治療後も定期的な経過観察が欠かせません。
食事療法
食事療法を行うために、アレルゲンとなる食物を特定することが重要です。アレルゲンとなる食べものを回避することで好酸球食道炎の発生を予防することができます。食物アレルギーの特定には、食事日記をつけることや、アレルギー検査が必要となります。
好酸球食道炎でお悩みの方へ
好酸球性食道炎は慢性的な病気であり、治療には時間がかかる場合もあります。だからこそ、症状が進行する前に早期に適切な治療を受けることが重要となります。好酸球食道炎に関してご不明な点や些細な症状がありましたらお気軽に四谷内科・内視鏡クリニックまでご相談ください。