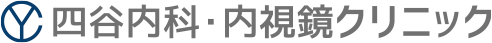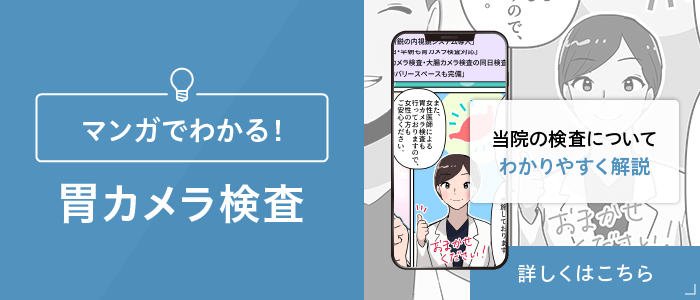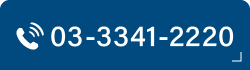食道がんとは
 食道がんとは、口から胃へとつながる食道に発生する悪性腫瘍のことを指します。食道の内側は粘膜で覆われており、この粘膜の細胞が何らかの原因で異常をきたし、がん化することにより発症します。食道がんは日本をはじめとするアジア諸国で比較的多く見られるがんの一つで、特に中高年の男性に多く発症すると言われています。日本では、食道がんの約90%以上が「扁平上皮がん」と呼ばれるタイプで、食道の内面を覆う扁平上皮細胞から発生するものとなります。一方、欧米では「腺がん」というタイプが増えており、これはバレット食道と呼ばれる病変に関連して発生することが知られています。食道がんは進行が早く、初期には症状が乏しいため、発見が遅れやすい特徴があります。しかし、早期に発見できれば治療することが可能なため、定期的な胃内視鏡検査や生活習慣の見直しを行うことが重要となります。
食道がんとは、口から胃へとつながる食道に発生する悪性腫瘍のことを指します。食道の内側は粘膜で覆われており、この粘膜の細胞が何らかの原因で異常をきたし、がん化することにより発症します。食道がんは日本をはじめとするアジア諸国で比較的多く見られるがんの一つで、特に中高年の男性に多く発症すると言われています。日本では、食道がんの約90%以上が「扁平上皮がん」と呼ばれるタイプで、食道の内面を覆う扁平上皮細胞から発生するものとなります。一方、欧米では「腺がん」というタイプが増えており、これはバレット食道と呼ばれる病変に関連して発生することが知られています。食道がんは進行が早く、初期には症状が乏しいため、発見が遅れやすい特徴があります。しかし、早期に発見できれば治療することが可能なため、定期的な胃内視鏡検査や生活習慣の見直しを行うことが重要となります。
食道がんの主な原因
 食道がんの発症には、生活習慣が深く関与していると言われています。食道がんの最も大きなリスク要因は「飲酒」と「喫煙」となります。特にアルコールに含まれるアセトアルデヒドという物質は、細胞を傷つける性質があり、がんの発生を促進すると考えられています。アルコールの代謝に関与する酵素の遺伝的な違いによって、アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、より食道がんのリスクが高くなります。また、喫煙は食道粘膜に慢性的な刺激を与えるため、食道がんの発症リスクを大きく高めると言われています。その他にも、熱い飲み物の頻繁な摂取、慢性的な胃食道逆流症(GERD)、食道アカラシア(食道の運動障害)、栄養不足(特にビタミンA、C、Eの不足)なども関与しているとされています。
食道がんの発症には、生活習慣が深く関与していると言われています。食道がんの最も大きなリスク要因は「飲酒」と「喫煙」となります。特にアルコールに含まれるアセトアルデヒドという物質は、細胞を傷つける性質があり、がんの発生を促進すると考えられています。アルコールの代謝に関与する酵素の遺伝的な違いによって、アセトアルデヒドの分解が遅い体質の人は、より食道がんのリスクが高くなります。また、喫煙は食道粘膜に慢性的な刺激を与えるため、食道がんの発症リスクを大きく高めると言われています。その他にも、熱い飲み物の頻繁な摂取、慢性的な胃食道逆流症(GERD)、食道アカラシア(食道の運動障害)、栄養不足(特にビタミンA、C、Eの不足)なども関与しているとされています。
胃食道逆流症
胃食道逆流症(GERD)は、胃酸や胃内容物が逆流し、食道の粘膜を刺激することで、胸やけや喉の違和感、咳などの症状を引き起こす病気です。食道は本来、胃酸に対する防御力が弱いため、繰り返し酸が逆流すると炎症を起こしやすくなります。主な原因には、加齢や肥満、過食、姿勢の影響、下部食道括約筋の緩みなどがあり、生活習慣が深く関わっていると言われています。症状が軽度であれば、食後すぐに横にならない、脂っこい食事を避けるなどの生活改善で改善が可能となります。しかし慢性的な逆流が続くと、「バレット食道」と呼ばれる前がん病変に進展することもあるため、長引く胸やけなどの症状がある場合は、消化器内科で内視鏡検査を受けるようにしましょう。
食道がんのメカニズム
食道がんは、食道粘膜の細胞がさまざまな刺激により遺伝子の異常を蓄積し、がん化することで発症します。日本で一般的なタイプである「扁平上皮がん」は、アルコールやタバコなどの化学的刺激により食道粘膜が慢性的に傷つけられ、修復を繰り返すうちに細胞に突然変異が生じ、がん化を引き起こすと言われています。一方で、米国などに多い「腺がん」は、胃酸の逆流により食道下部が長期間酸にさらされることで、粘膜が胃や腸のような組織に変化(バレット食道)し、そこからがん化すると言われています。いずれの場合も、がん細胞が食道の壁を深く浸潤し、周囲の臓器やリンパ節へと広がる性質を持っており進行が極めて速いと言われています。
食道がんの症状
 食道がんは、初期症状がほとんど現れないことが多く、発見が遅れることも多いと言われています。悪化すると「食べ物がつかえる感じ(嚥下困難)」を感じることが多くなります。最初は固いものが飲み込みづらくなり、徐々に柔らかい食べ物や水分でも飲み込みにくさを感じるようになります。他にも、「胸の痛みや違和感」「喉のつかえ感」「体重減少」「声のかすれ」「咳」「吐血」などが見られることもあります。特に、声帯の神経にがんが浸潤すると声のかすれが起き、気道へ転移や圧迫があると咳や呼吸困難が出現することもあります。これらの症状が出た時点で食道がんがかなり進行していることも少なくありません。そのため、症状がなくても定期的な胃内視鏡検査を受けることが早期発見の鍵となります。
食道がんは、初期症状がほとんど現れないことが多く、発見が遅れることも多いと言われています。悪化すると「食べ物がつかえる感じ(嚥下困難)」を感じることが多くなります。最初は固いものが飲み込みづらくなり、徐々に柔らかい食べ物や水分でも飲み込みにくさを感じるようになります。他にも、「胸の痛みや違和感」「喉のつかえ感」「体重減少」「声のかすれ」「咳」「吐血」などが見られることもあります。特に、声帯の神経にがんが浸潤すると声のかすれが起き、気道へ転移や圧迫があると咳や呼吸困難が出現することもあります。これらの症状が出た時点で食道がんがかなり進行していることも少なくありません。そのため、症状がなくても定期的な胃内視鏡検査を受けることが早期発見の鍵となります。
食道がんの診断方法
 食道がんの診断には胃内視鏡検査が必要となります。内視鏡を用いて食道の内側を直接観察し、がんが疑われる部位があればその組織を採取(生検)し、病理検査でがん細胞の有無を確認することが可能です。生検を行うことで「扁平上皮がん」や「腺がん」などの種類、悪性度を把握することができます。またがんの進行度(ステージ)を評価するために、CT検査やMRI、PET-CTなどを行う場合もございます。CT検査やMRI検査では、食道の壁への浸潤の深さや、リンパ節・他臓器への転移の有無を調べることができます。食道がんは、早期がんであれば、内視鏡治療のみで完治する可能性もあるため、早期の発見が必要となります。
食道がんの診断には胃内視鏡検査が必要となります。内視鏡を用いて食道の内側を直接観察し、がんが疑われる部位があればその組織を採取(生検)し、病理検査でがん細胞の有無を確認することが可能です。生検を行うことで「扁平上皮がん」や「腺がん」などの種類、悪性度を把握することができます。またがんの進行度(ステージ)を評価するために、CT検査やMRI、PET-CTなどを行う場合もございます。CT検査やMRI検査では、食道の壁への浸潤の深さや、リンパ節・他臓器への転移の有無を調べることができます。食道がんは、早期がんであれば、内視鏡治療のみで完治する可能性もあるため、早期の発見が必要となります。
胃カメラ検査
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、細いカメラ付きの管を口または鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の内側を直接観察する検査です。食道裂孔ヘルニアの場合には、胃カメラ検査にて、胃の一部が胸部に入り込んでいないか、胃酸の逆流による食道の炎症がないかを詳しく確認します。胃カメラ検査は数分で終了し、局所麻酔や鎮静剤を用いることで苦痛も軽減することは可能です。
食道がんの治療
食道がんの治療は、がんの進行度(ステージ)や患者様の全身状態、年齢、合併症の有無などによって異なります。早期がんの場合は、内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)といった内視鏡治療で完治が期待できます。進行がんでは、外科的手術が基本となりますが、食道の位置や周囲臓器との関係から高難度な手術になることが多く、術前術後の全身管理も必要となります。また、がんのステージによっては手術前後に化学療法(抗がん剤)や放射線療法を組み合わせた治療が行われることもあります。さらに、治療後は再発防止や生活の質の維持のために、定期的なフォローアップが必要となります。食道がんは進行が早いために、症状が出る前に定期的な胃カメラ検査を受けて頂くことが大切となります。
食道がんのアフターフォロー
食道がんの治療が終わった後も、安心して日常生活を送るためにはアフターフォロー(経過観察)がとても重要となります。特に手術や化学放射線療法を受けた方は、再発の有無や治療による後遺症の管理、全身の栄養状態や生活習慣の見直しなど、多面的なサポートが必要となります。当院では定期的な血液検査や内視鏡検査の必要性を見極めながら、基幹病院との連携を取りつつ再発防止策をご提案させていただきます。術後に起こりやすい嚥下障害や体重減少、胃食道逆流症などの症状に対して、食事指導や薬物療法を通じて患者様の状態にあわせた治療方法を実施させていただきます。患者様が安心して通院できる環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
食道がんでお悩みの方へ
食道がんは早期では自覚症状が乏しい一方で、進行すると食事がしづらくなり、日常生活に支障をきたすこともあります。しかし、早期発見・早期治療によって完治を目指すことが可能な病気です。特に初期段階で発見されれば、内視鏡による低侵襲な治療だけで済むこともあり、身体への負担も少なくて済みます。食道がんに関してご不明な点や些細な症状がありましたらお気軽に四谷内科・内視鏡クリニックまでご相談ください。